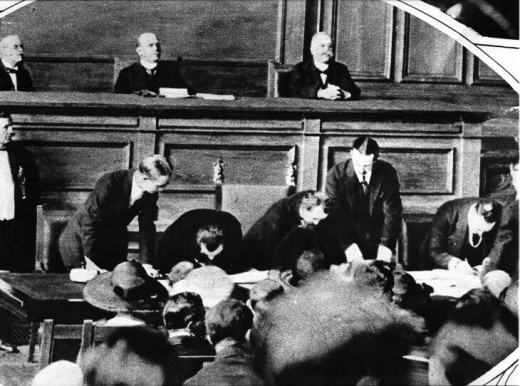カルロヴィッツ条約の内容─ヨーロッパへの玄関口ハンガリーを失う

カルロヴィッツ条約の締結場面(1699年)
カルロヴィッツ(現セルビアのスレムスキ・カルロヴツィ)で行われた和平条約の交渉風景を描いた版画。この条約でオスマン帝国は多くの領土を失った。
出典:Unknown German artist from the Low Countries / Wikimedia commons Public Domain
オスマン帝国にとってハンガリーって、単なる“征服地”じゃなくて、ヨーロッパへの橋頭保=攻めの起点みたいな場所だったんです。
でも17世紀の終わり、帝国はこの超重要エリアをついに失うことになります。
きっかけは1699年のカルロヴィッツ条約――これはオスマン帝国が「防戦一方の時代」へと突入する決定打でした。
今回は、この条約とハンガリー喪失の意味について、歴史の流れとともに分かりやすく見ていきましょう!
ハンガリーはなぜオスマンにとって重要だった?
まず、なんでそこまでハンガリーにこだわってたの?って話から。
中央ヨーロッパの“玄関口”だった
ハンガリーはドナウ川流域に広がる広大な平原で、東から西へ、バルカンからドイツ・ポーランド方面へ向かう交通・軍事の大動脈上にあります。
つまりここを押さえておけば、神聖ローマ帝国にもプレッシャーをかけられる、そんな戦略的な拠点だったんですね。
1530年代からオスマンの支配下に
スレイマン大帝がモハーチの戦い(1526年)でハンガリー王国を撃破し、その後、中部ハンガリーは完全なオスマン直轄領に。
ブダにパシャ(総督)を置き、イスラーム文化が広がる珍しいヨーロッパ地域にもなっていました。
カルロヴィッツ条約が結ばれるまでの流れ
でも、17世紀後半になるとオスマン帝国の勢いにも陰りが出てきます。
第二次ウィーン包囲の失敗(1683年)
カラ・ムスタファ・パシャ率いる大軍が、再びウィーンを包囲。
でもヨーロッパ側の連携(特にポーランドのヤン3世の突撃)によって大敗し、ここから一気に「連戦連敗モード」に突入していきます。
神聖同盟軍の総反撃とオスマンの崩壊
オーストリア・ポーランド・ロシア・ヴェネツィアが結成した対オスマン神聖同盟による反攻が始まり、1697年のゼンタの戦いでは、オスマン軍が壊滅的敗北を喫します。
そして翌1699年、オスマン帝国が初めて“領土を譲る”側に回るカルロヴィッツ条約が結ばれるんです。
カルロヴィッツ条約の内容と衝撃
この条約、オスマンにとっては歴史的ターニングポイントとなるものでした。
オーストリアに“ほぼ全部のハンガリー”を譲渡
- 中部ハンガリー全域(≒直轄領だった部分)
- トランシルヴァニア(東ハンガリーの山岳地帯)
- スラヴォニアなど周辺地域
以上を完全にオーストリアに引き渡し、中央ヨーロッパからの撤退を意味する条項が盛り込まれます。
初の「ヨーロッパ式国際条約」
カルロヴィッツ条約は、外交儀礼や条文の形式など、西洋型の条約スタイルで作られた初めての文書でもありました。
つまりここから“東洋の帝国”オスマンが、西洋の外交ルールに組み込まれ始めたという意味もあったんです。
ハンガリー喪失が意味するもの
じゃあ、ハンガリーを失ったことで、オスマン帝国にはどんな影響があったのか?
攻勢から守勢へ、“戦略の反転”
もはやウィーンや中欧を狙う余地はなくなり、国境の防衛=防戦一方へと転じることになります。
これは単なる領土喪失じゃなくて、“帝国としての勢い”の喪失でもありました。
ヨーロッパ諸国の“舐められ始め”
この条約をきっかけに、ヨーロッパ列強は「オスマン帝国=脅威」ではなく、“押せば引く相手”として見るようになります。
ここから東方問題――つまり、オスマンの領土をどこがどう切り取るか?という外交ゲームが始まっていくんですね。
カルロヴィッツ条約によるハンガリー喪失は、単なる“国境線の変更”ではありません。
それはオスマン帝国が攻めの時代を終え、防戦と衰退の時代に入った決定的な瞬間だったんです。
この出来事から、帝国はじわじわと“ヨーロッパに飲まれていく存在”へと変わっていきます。
まさに「オスマンが世界の主役から降りた日」とも言える、歴史の分岐点だったんですね。