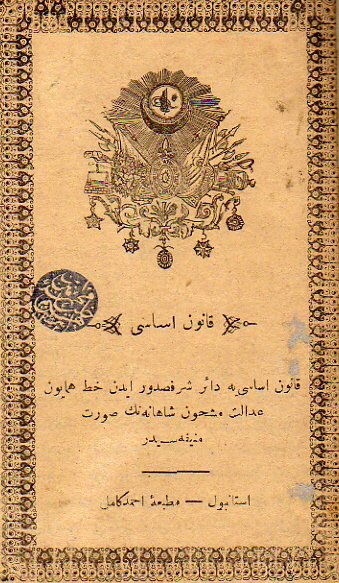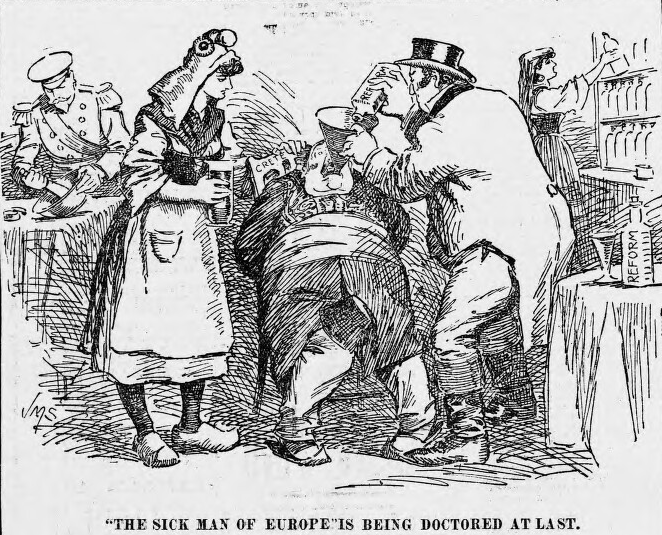オスマン帝国の成り立ちとは?─トルコの前身国家

トルコの国旗
現トルコ共和国は、文化や領土、政治機構の一部をオスマン帝国から継承しつつ、「帝国のかたち」や「イスラム的権威」は否定していることに注意したし
─出典:Hüseyin SevgiによるPixabayからの画像より─
オスマン帝国って聞くと、なんだか壮大で長く続いた大帝国のイメージが強いですよね。確かに、その領土はアジア・ヨーロッパ・アフリカにまたがり、600年以上も続く一大国家でした。でもそんな帝国も、最初はとても小さな出発点から始まったんです。
今回は、「オスマン帝国がどこから来たのか?」をテーマに、その起源となる背景をたどっていきます。そもそもトルコの地にいたのは誰だったのか?オスマン帝国がどうやって誕生したのか?そしてその前にはどんな国や勢力がいたのか?――などなどオスマン帝国の成り立ちにまつわる疑問に迫っていきます。
オスマン帝国の前にあった勢力
「オスマン帝国」の前夜を彩った国家や遊牧勢力について見ていきましょう。
セルジューク朝
11世紀後半、アナトリアに進出していたセルジューク朝は、オグズ系トルコ人によるイスラーム王朝です。彼らは、1071年のマラズギルトの戦いで東ローマ(ビザンツ)帝国を破り、アナトリアへのトルコ人の定住を決定づけました。
ルーム・セルジューク朝
その後、セルジューク朝の分派としてルーム・セルジューク朝がアナトリアに成立します。「ルーム」はローマ(東ローマ)の意味で、この王朝はかつての東ローマ領であるアナトリアを支配していたんですね。文化的にも経済的にも発展したこの国が、のちのオスマン帝国へとつながる土台となるわけです。
モンゴルの圧力と分裂
ところが13世紀半ばになると、モンゴル帝国の西方遠征の影響でルーム・セルジューク朝は弱体化。各地のトルコ系ベイ(首長)たちが独立を強めていきます。いわば“小国割拠”の時代へ突入し、その中のひとつが後のオスマン帝国へと成長するわけです。
建国者オスマン1世の登場
では、その「小さなベイリク(首長国)」のひとつであるオスマン家が、なぜ頭ひとつ抜けて帝国化できたのか?
オスマン家の出自
オスマン家は、モンゴルの侵攻を逃れて西アナトリアへ移住してきたトルコ系の部族「カイ族」に属していました。彼らは遊牧民出身で、柔軟な組織構造と軍事力を誇っていたんです。
辺境という地の利
オスマン家の拠点は、東ローマ帝国との国境線に位置していました。この「辺境(ウジュ)」の地では、ジハード(聖戦)に名を借りてキリスト教勢力への攻撃が奨励され、若くて有能な戦士たちが続々と集まってきたんです。つまり、軍事的な“活力”があふれる場所だったわけですね。
オスマン1世のカリスマ性
そして、13世紀末にこの地で頭角を現したのがオスマン1世(1258頃 - 1326)。彼はルーム・セルジューク朝の混乱をうまく利用して自立し、さらに周辺のキリスト教勢力に対する戦いで名声を得ます。その名声がイスラーム世界でも評価され、国家としての正統性も獲得するようになるんです。
「帝国化」への道のり
まだまだこの時点では「オスマン“帝国”」ではありませんが、着実にその土台が築かれていきました。
ガジー(戦士)国家としての成長
オスマン家の戦いは「ガズァー(聖戦)」とみなされていたため、イスラーム世界の若者たちが「聖戦に参加したい!」と志願して集まり、戦力がどんどん強化されていきました。こうして軍事力を軸にした拡張が進んだのです。
多民族支配の始まり
征服した地域には、ムスリムだけでなくギリシア系キリスト教徒やアルメニア人なども多く住んでおり、彼らをうまく取り込む寛容な姿勢も取られました。後に整備されるミッレト制度の原型はこの時期に生まれたとも言われます。
帝国と呼ばれるようになるまで
オスマン家が「帝国」として本格的に認識されるのは、コンスタンティノープルを制圧したメフメト2世(在位:1451–1481)の時代以降。ただ、すでに14世紀末には広大な領土を支配し、バルカン半島にまで進出していたことから、「帝国」としての実体は徐々に整っていたんですね。
このように、オスマン帝国は何もないところから突然生まれたわけではなく、モンゴルの混乱・セルジューク朝の衰退・辺境の活力といった複雑な背景を経て成り立ったのです。そして、遊牧的な柔軟さと宗教的な正当性の両輪が、のちの大帝国へと成長する土台をつくった…これが「トルコの前身国家」としてのオスマン帝国の出発点だったわけですね。