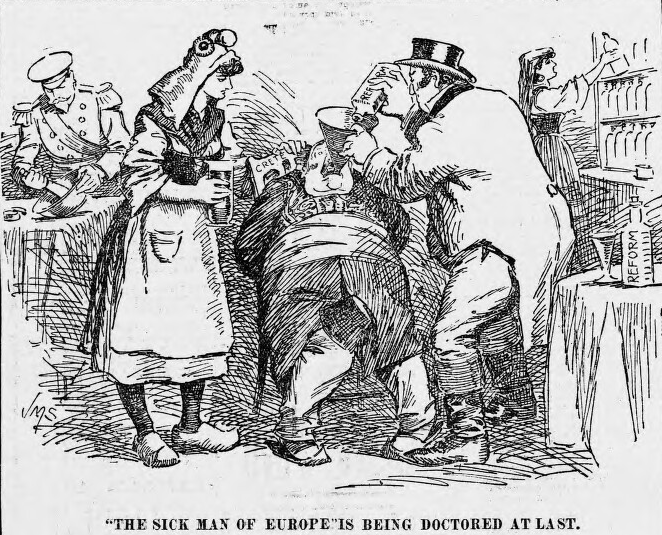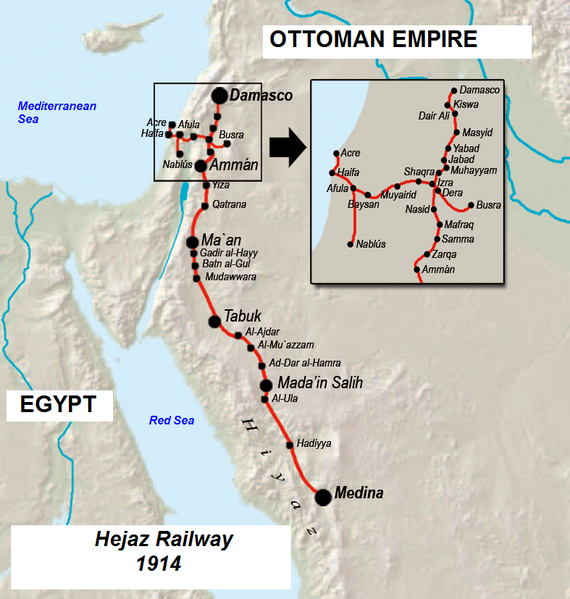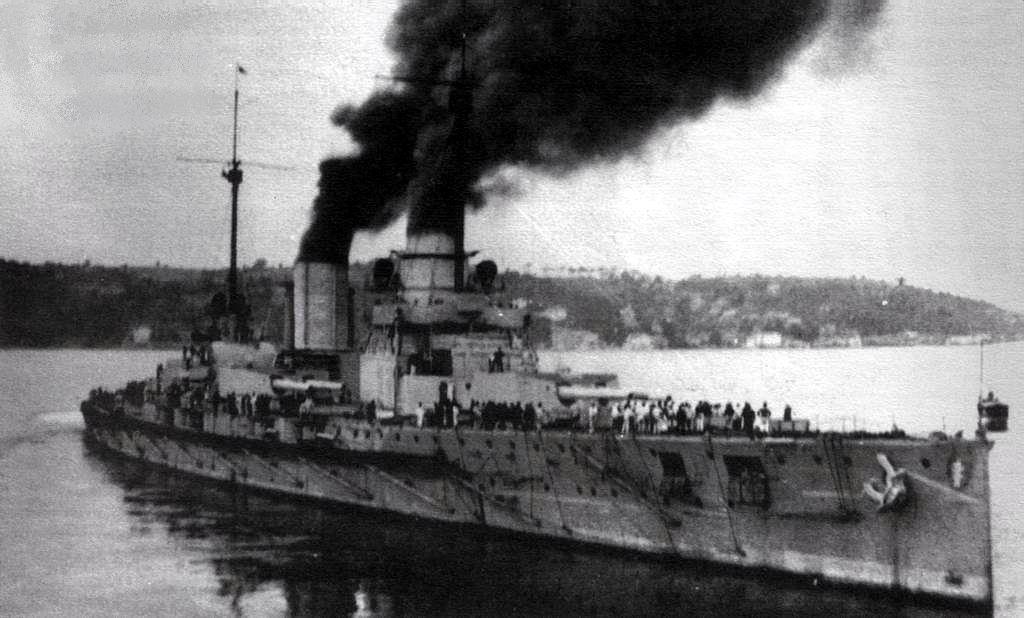オスマン帝国とベネチアの関係─海賊と商人国家の地中海劇場

レパントの海戦(17世紀の絵画)
ベネチアが神聖同盟の一員として参加し、オスマン帝国の地中海制海権に打撃を与えた大規模海戦
出典:作者不明 / Wikimedia Commons Public domainより
オスマン帝国とベネチア共和国――この2国の関係は、まさに「海賊と商人」のようなスリル満点の愛憎ドラマ。
地中海をはさんでにらみ合いながらも、時には手を組み、時には血で血を洗う戦争を繰り返してきたんです。
オスマンは軍事と制海権で攻め、ベネチアは貿易と外交でかわす――このせめぎ合いが、中世~近世地中海世界を大きく動かしていきます。
今回は、そんな緊張感たっぷりのオスマン×ベネチア関係を、時代を追って見ていきましょう!
最初からバチバチだった?
オスマン帝国とベネチアの関係は、最初から友好的だったわけではありません。
むしろ最初はオスマンの地中海進出=ベネチアの“縄張り”への侵略だったんです。
オスマンの台頭にベネチアがビビる
15世紀、オスマン帝国がアナトリアからどんどん拡大し、ギリシャやエーゲ海の島々に進出し始めます。
これに焦ったのが、地中海貿易で大もうけしてたベネチア。
商人国家としての生命線が、オスマンの軍事力に脅かされ始めたんですね。
最初の衝突は1453年のコンスタンティノープル陥落後
東ローマ帝国の崩壊とともに、オスマンが地中海の玄関口を完全に押さえるようになります。
ベネチアはこれを見て、通商条約を結んで一時的に妥協。
でもこの“仲直り”はすぐに破られ、16世紀にはいよいよ本格的な戦争が始まるんです。
戦争・講和・また戦争…の繰り返し
16〜17世紀は、オスマンとベネチアが交互に海と島を取り合う時代。
まるで“憎しみを抱えた同居人”のような関係でした。
キプロス戦争(1570〜73)とレパントの海戦
ベネチアが支配していたキプロス島をオスマンが攻め落とし、それに対してベネチアは教皇やスペインと連合。
このとき起きたのが1571年のレパントの海戦です。
結果はキリスト教連合の大勝利で、オスマン帝国にとって初の大きな海軍敗北でした。
でも実はそのあともオスマンは巻き返し、キプロス自体はちゃんと確保してるんですよね。
つまり戦争では負けたけど、島は取ったもん勝ちだったという話。
クレタ戦争(1645〜69)ではオスマンが完全勝利
ベネチアが長年保持していたクレタ島を巡る戦争では、最終的にオスマン軍がじわじわ包囲し、根気勝ち。
24年も続いた消耗戦の末に、クレタ島はオスマン帝国のものになります。
このあたりから、ベネチアの力は徐々に陰りを見せていくんです。
でも商人国家らしく“しぶとく”生き残る
何度もやられながら、ベネチアはオスマン帝国と通商関係を維持しようとがんばります。
というのも、ビジネスさえ回れば国家は生き延びられるってのが、ベネチアのモットーだったから。
オスマンとの貿易協定を何度も更新
ベネチアは軍事的に不利でも、繊維・香料・金属製品などを輸出して、オスマン帝国内では重要な経済パートナーとしての立場をキープ。
逆にオスマンも、「ベネチア商人に関税収入を頼ってる部分もあるしな…」ってことで、敵だけど切れない関係として扱っていたんです。
“海賊と商人”の皮肉な共存関係
オスマンの私掠船(いわば国家公認の海賊)と、ベネチアの交易船は、海では戦ったり、港では交渉したりという不思議な共存を続けていました。
戦いながらも商売する――それが中世地中海のリアルな国際関係だったんですね。
オスマン帝国とベネチアの関係は、戦争と貿易が交互に来る“愛と憎しみの地中海劇場”でした。
まるで「殴り合いながら取引する」みたいな関係。
オスマンが軍事で押し、ベネチアが経済と外交で粘る――海賊と商人国家の攻防は、地中海の歴史を動かす大きな原動力だったんです。