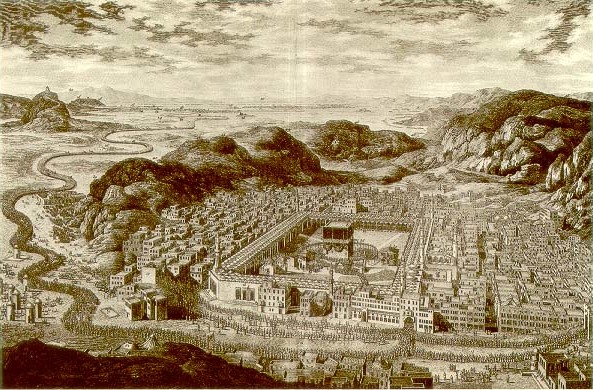オスマン帝国のクルド人事情─自治か抑圧か…ゆらぎ続けた共存体制

オスマン帝国所属クルド騎兵部隊(1918年)
第一次世界大戦中、オスマン帝国軍に編成されたクルド人による騎兵部隊
出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより
オスマン帝国とクルド人――どちらも中東の歴史を語るうえで欠かせない存在ですが、この関係は「味方」と「支配下の民」のあいだを行ったり来たりする、なかなか複雑なものでした。
時には自律的な同盟者、時には反乱を起こす厄介な存在として、オスマン帝国はクルド人と向き合ってきたんです。
今回はこの“揺れる共存関係”を、歴史的背景とともに解説していきます!
そもそもクルド人ってどんな人たち?
まずはざっくり、クルド人とは何者なのか?を確認しておきましょう。
この理解がないと、オスマンとの関係もぼんやりしてしまいます。
山岳地帯に暮らす“非アラブ・非トルコ”のイスラーム教徒
クルド人は、中東のイラン・イラク・トルコ・シリアの国境地帯にまたがる山岳地帯に住む民族グループです。
言語はインド=ヨーロッパ語族のクルド語、宗教は主にスンナ派イスラームですが、地域によってはシーア派やヤズィーディー派などもいます。
つまり文化・宗教はオスマンと近いけど、民族的には別という、ちょっと特殊な立ち位置なんですね。
独立した国家を持たなかった“地域勢力”
クルド人は長らく部族単位での自治・統治を行っていて、オスマン帝国が登場するまでに統一された“クルド国家”を築いたことはありません。
そのぶん、外部の大国との関係の中で自治と服属のバランスを探るスタイルを取ってきました。
オスマン帝国との“協力関係”の始まり
オスマン帝国が15〜16世紀に東方へ拡大する中で、クルド人との関係は一気に重要になっていきます。
サファヴィー朝との対抗でクルドを味方に
16世紀、オスマン帝国は東のシーア派サファヴィー朝とバチバチに対立します。
その際、オスマン側はスンナ派のクルド人部族を味方に引き入れ、国境地帯の防衛を任せるようになります。
ここでは「敵の敵は味方」という形で、クルド人が半自治的な“緩衝地帯”の担い手になったわけです。
“忠誠の見返り”に自治が許される
特に16世紀のイディルミルザ条約以降、一部のクルド部族は独自の支配権を持ちつつオスマンに臣従する形式が定着。
これはまさに、中央集権ではなく「間接支配」というオスマンらしい柔軟さが出たポイントでもあります。
でも時代が進むと摩擦も増えていく
近世までは比較的うまくいっていたオスマンとクルドの関係ですが、19世紀以降は次第に緊張が高まっていきます。
中央集権化と反乱の連鎖
タンジマート改革などでオスマン帝国が中央集権化・徴税制度の強化を進めると、それまで半独立状態だったクルド首長たちは「干渉が多くなってきたぞ…」と反発。
その結果、1830年代〜1880年代にかけて複数のクルド反乱が発生します。
“オスマン臣民”としての同化政策も
19世紀末、スルタン・アブデュルハミト2世の時代にはスンナ派の統合(汎イスラーム主義)が推進され、クルド人にも「オスマン帝国の忠実なイスラーム臣民」としての役割が期待されました。
でもそれは同時に、民族的な独自性の抑圧につながっていったんです。
オスマン帝国とクルド人の関係は、最初は共通の敵(サファヴィー朝)への対抗から生まれた“戦略的共存”でした。
でも時代が進むにつれて、中央集権との摩擦や民族的自立の動きが目立つようになり、自治と抑圧のはざまで揺れ続けた関係になっていったんです。
この歴史は、現代のクルド問題を理解するうえでも、避けて通れない大事な視点なんですよ。