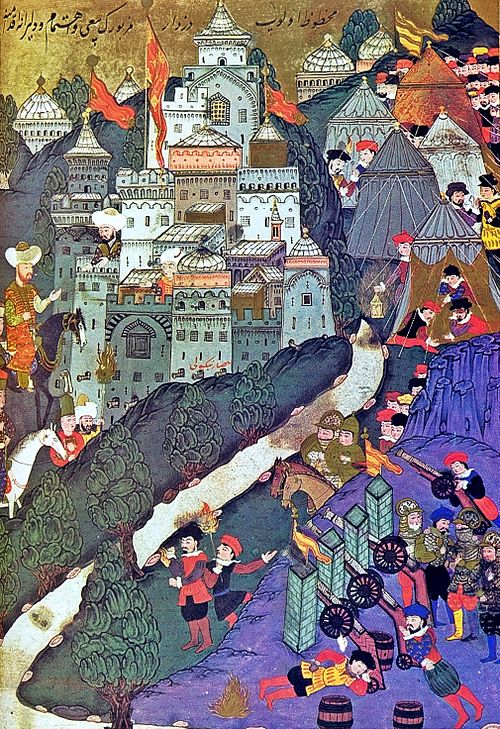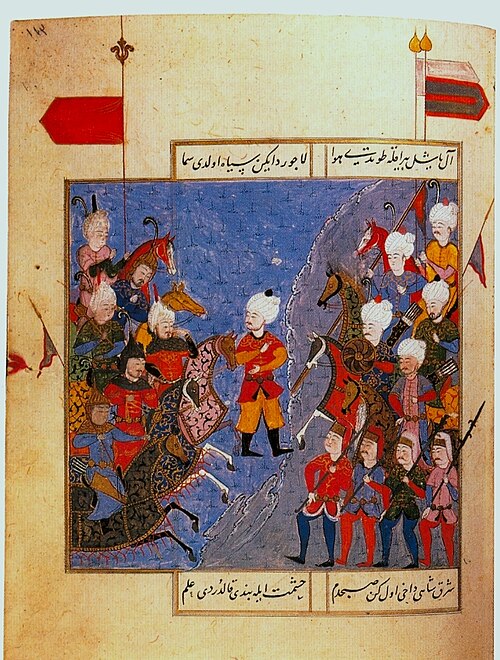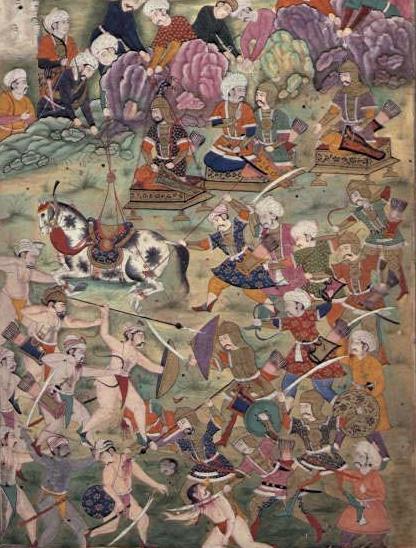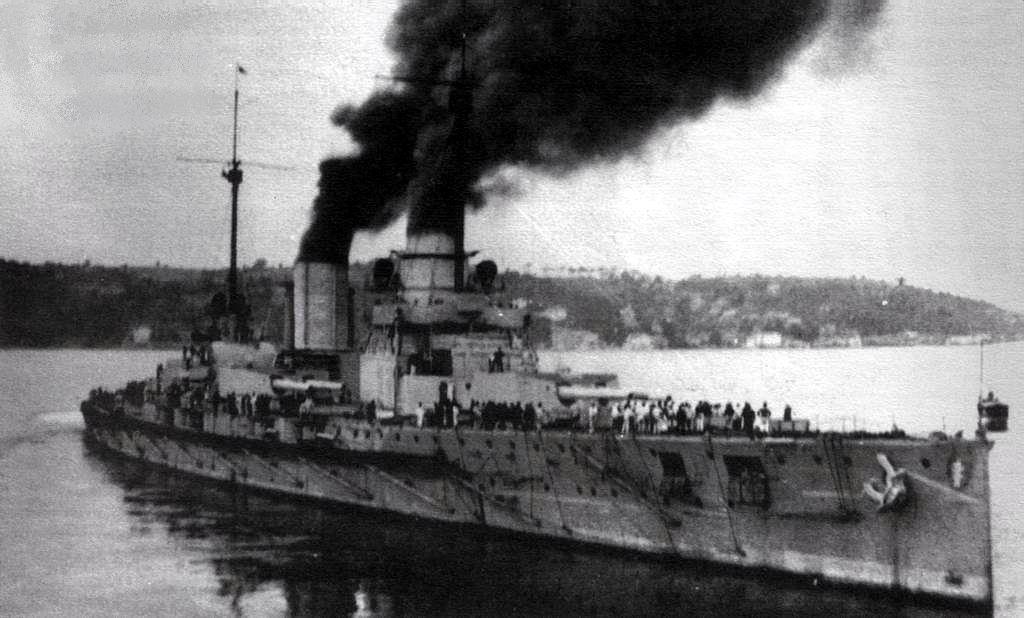オスマン帝国と日露戦争 ─ ロシアの敗北とその影響とは?
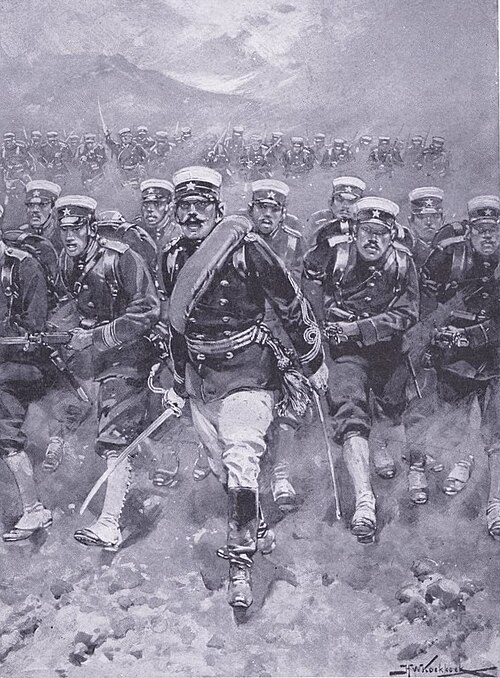
日露戦争・日本帝国陸軍歩兵の突撃
日露戦争でのロシアの敗北は、「アジアの小国でも欧州列強に勝てる」という衝撃と希望を与え、オスマン帝国の改革派・民族主義者たちを鼓舞した
出典:Johannes Hermannus Barend Koekkoek / Wikimedia commons Public domainより
20世紀のはじめ、世界が「帝国から近代国家」へと大きく揺れ動いていた中で、ある戦争が各国に衝撃を与えました。そう、1904〜1905年の日露戦争です。
一般的には「アジアの小国・日本がロシアに勝った!」っていう出来事として知られてますが、実は遠く離れたオスマン帝国もこの戦争をガッツリ注目していて、むしろめちゃくちゃ影響を受けてたんです。
以下で、オスマンが日露戦争から何を感じて、どう動いたのかを解説していきますね!
オスマン帝国はなぜ日露戦争をそんなに気にしてたの?
「え、アジアの戦争なんて、オスマンには関係ないんじゃ?」って思いそうですが、当時のオスマンにとってはまさに他人事じゃない話だったんです。
共通の“ライバル”がいた
オスマン帝国とロシア帝国は、実は18世紀からずーっとケンカしてる宿敵同士。
黒海やバルカン半島、カフカスの支配をめぐって何度も戦争してきたんですよね。
そんな相手にアジアの日本が勝った――って聞いたら、そりゃオスマンも「え、マジで!?希望あるじゃん!」ってなるわけです。
「西洋に勝てる東洋」が現れた衝撃
当時のオスマン帝国は、近代化を急ぎながらもヨーロッパ列強に押され気味。
そこに登場したのが、西洋化に成功した“非白人国家”の勝利という、まさに“歴史の事件”。
この出来事は、オスマンの知識人・軍人・改革派にとってものすごく勇気をくれるものでした。
実際にどんな影響があったの?
日露戦争の衝撃は、オスマン帝国に改革への再点火、そして帝国意識の再構築を促すような、じわじわ効いてくるインパクトを与えました。
軍人たちに火がついた
特に影響を受けたのが若手の将校たち。
「日本は天皇のもとで近代化に成功した。うちも君主(スルタン)だけに頼ってたらアカンやん!」みたいな議論が広がっていきます。
この流れが、後の青年トルコ運動や1908年の立憲革命にもつながっていくんです。
日本のモデル化が始まる
実際にオスマンの知識人や新聞は、「日本はどうやって強くなったのか」って研究しまくります。
- 明治維新のやり方
- 教育制度の改革
- 国民意識の育て方
こうしたことを、「日本に学べ」という視点で論じる記事や本がたくさん出てくるんです。
もっと広い意味での“イスラーム世界”への影響も
オスマン帝国って、当時スルタン=カリフ(イスラームの指導者)でもあったので、日露戦争の影響は帝国内だけにとどまらなかったんです。
ムスリム世界全体が沸いた
「非キリスト教国が西洋列強に勝った」っていうのは、イスラーム世界にとっても一種の宗教的な希望みたいなものでした。
特にインド、エジプト、イランなどの知識人もオスマン同様に熱狂。「オスマンも日本みたいにやれるはず!」っていうムードが一気に広がります。
“反ロシア感情”とセットで爆発
もともとロシアは、イスラーム圏に侵出してきた最大のキリスト教勢力だったので、そこに負けを与えた日本はヒーロー的存在にもなりました。
オスマン帝国では、日章旗が描かれた陶器やポスターなんかも登場してたって記録もあるんですよ。
日露戦争の勝利は、オスマン帝国にとって「時代が変わるかもしれない」っていう希望のシンボルでした。
日本が西洋列強に勝ったことで、オスマンの軍人や改革派たちの心に火がつき、近代化や憲政への道を加速させるきっかけになったんです。
遠く離れたアジアの出来事が、帝国の末期をどう生き抜くかという視点に大きなインスピレーションを与えていた――それが日露戦争のもうひとつの歴史的な意味なんですね。