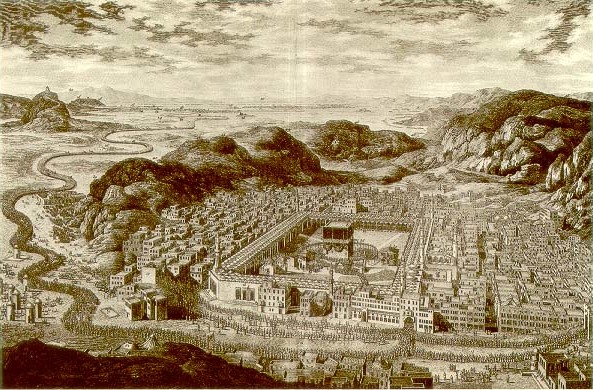オスマン帝国の教育事情─学校はあった?教育体系の変遷を知ろう

ベヤズィト州立図書館
オスマン帝国の教育制度改革の一環として、1884年に公立図書館として設立
帝国の教育普及と学術保存に大きく寄与した
出典:Wikimedia Commons / Public Domain
オスマン帝国って聞くと、宮殿とか軍隊とか派手なイメージが先に来るかもしれませんが、じつは教育制度もかなり独特で、しかも時代によって大きく変化してるんです。最初は宗教中心だったのが、だんだんと“近代化”を意識したスタイルへと進化。この記事ではそんなオスマン帝国の教育の変遷を、時代ごとにわかりやすく紹介していきます。
伝統的な教育制度
オスマン帝国の教育は、もともとイスラームの価値観にどっぷりと根差したものだったんです。
スブヤン・メクトゥブ:初等教育の場
最初に通うのが、いわば“読み書きそろばん”の学校にあたるスブヤン・メクトゥブ。ここではまずクルアーン(コーラン)の暗唱を中心に、読み書きや基本的な道徳を学びました。男子だけでなく女子も通うことができ、比較的幅広い層に教育の門戸が開かれていたのです。
マドラサ:高等宗教教育の中核
その次のステップがマドラサ。ここではイスラーム法学、神学、文法、論理学などを深く学びます。マドラサはモスクに付属していることも多く、神学者や法学者を目指す青年たちにとってエリート養成所のような存在でした。
エンデールン学院:官僚育成のための特別機関
王宮内にあったエンデールン学院は、特にデヴシルメ制で集められた少年たちを対象に、官僚や軍人として帝国の中枢を担わせるための教育機関。イスラム教義から言語、武芸、作法まで、トータルな人格教育が行われていました。
19世紀の教育改革
帝国が西欧列強との関係に悩まされるなか、教育もまた大きく変化していきます。
新式学校(ルシュディエ)の誕生
1839年のタンジマート改革以降、オスマン帝国は“近代化”を本気で目指し始めます。その象徴がルシュディエと呼ばれる新型の中等学校。ここでは算数・地理・歴史など、いわゆる“実学”が中心に据えられ、宗教一辺倒の旧来教育とは違う路線を打ち出しました。
ガラタサライ高等学校
特筆すべきなのが、1868年に創設されたガラタサライ高等学校。フランス語教育が行われ、ヨーロッパ式のカリキュラムが取り入れられました。卒業生の多くは官僚・外交官となり、近代オスマン国家の中核を担っていくことに。
軍事学校・専門学校の整備
とりわけ陸軍士官学校や海軍学校は、帝国の軍事改革の柱となりました。また医学校、工学校、教員養成所などの専門学校も続々と誕生し、「職業教育」が重視されるようになったのです。
宗教と世俗の狭間で
最終的に、教育は“イスラーム的価値観”と“西欧的合理主義”のあいだで大きく揺れることになります。
ウラマーと世俗官僚の対立
伝統的な宗教教育を守るウラマー(イスラム学者)と、近代化を推進した官僚層の間にはたびたび対立が。とくに学校教育の主導権をめぐって、政治の場でも激しい駆け引きがあったんです。
教育行政の中央集権化
1870年代以降、オスマン帝国は教育省(Maarif Nezareti)を中心に、国全体の学校を管理しようとします。これによって教育の質が向上する一方で、地域ごとの多様性や宗派的自由はやや制限される方向へと向かいました。
二重教育体制の矛盾
宗教系と世俗系の教育が並行して存在することで、価値観のねじれも起こります。たとえば、昼は近代的なルシュディエで「人権」や「合理主義」を学び、夜はモスクで「神の意志」に従う教えを聞く──そんな生徒たちが生まれたわけです。
このように、オスマン帝国の教育制度は、宗教と近代のあいだで揺れながら進化していきました。まさに“二つの世界をまたぐ”教育モデルだったといえるでしょう。